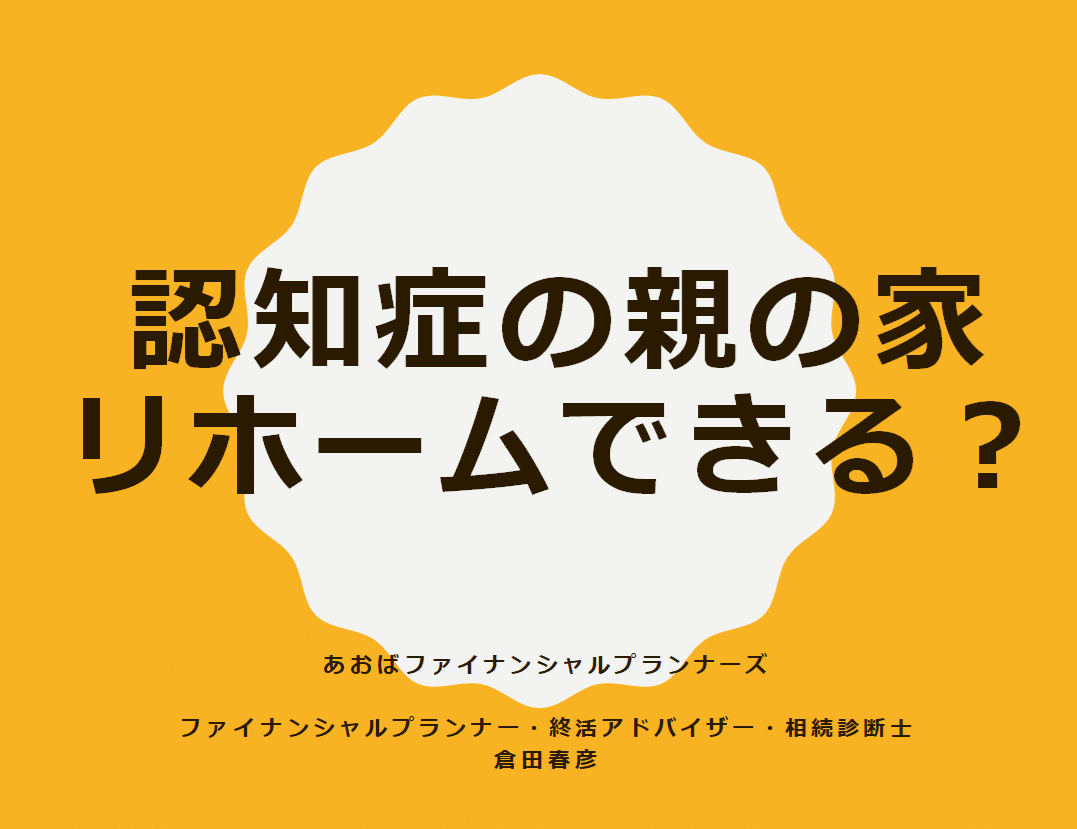 今日は認知症の親の家をリフォームするこことは出来るのか?というテーマでお話させて頂きます。
今日は認知症の親の家をリフォームするこことは出来るのか?というテーマでお話させて頂きます。
皆さん「2025年問題」ってご存じでしょうか?
主に日本社会が2025年に直面する大きな構造的な変化や課題を指す言葉です。「団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者になること」です。
主な内容と影響
1. 高齢化の急加速
団塊の世代(1947〜1949年生まれ)が2025年にすべて75歳以上の後期高齢者になります。650万人ほどいらっしゃるそうです。
高齢者人口の急増により、医療・介護の需要が急激に増える。
認知症患者も増加し、医療費・介護費の増大により、社会保障費が国の財政を圧迫。若年層や現役世代の保険料負担がさらに増える懸念。
2. 地方の衰退と空き家問題
高齢者の多くが地方に居住しており、過疎化が進行。首都圏でも空き家は増え続けています。
施設に入居したり相続されない空き家が急増し、治安や防災での保全面でのリスクが増える。
3.要介護になる主な原因(厚生労働省「国民生活基礎調査」などより)
要介護(要支援を除く)認定を受ける主な原因は以下のとおりです。
1位 認知症約18%徐々に進行し、生活全般に支障
2位 脳血管疾患(脳卒中など)約16%急性の発症が多く麻痺や言語障害などを伴う
3位 高齢による衰弱(老衰)約13%筋力・体力低下など
4位 骨折・転倒約12%特に女性や高齢者に多く、寝たきりの原因にも
5位 関節疾患(変形性膝関節症など)約10%歩行困難による要介護状態に
6位 その他の病気(がん、心臓病など)約31%多様な疾患が含まれる
4.認知症になる人の割合(日本)
● 全体の状況(厚生労働省・内閣府などの資料より)2025年には高齢者(65歳以上)の約5人に1人(約20%)が認知症になると予測されています。
具体的には、約700万人前後とされます。(※団塊世代が後期高齢者になることで急増)
5.親が判断能力を持っているかどうか?
・軽度の認知症で、親自身がリフォームの内容を理解し、同意できる場合は、親の同意を得て通常通り契約可能
・中等度~重度の認知症で、判断能力がないと見なされる場合は、法定代理人(成年後見人など)の関与が必要
6.家の名義は誰か
・家の所有者が親の場合、リフォーム工事を行うには所有者(親)の同意または代理人の同意が必要
・子供が所有者であれば、子供の判断でリフォーム可能
・共有名義の不動産は「全員の同意」が必要
・建て替えや大規模リフォーム(構造や価値に大きく関わる行為)は原則として共有者全員の同意が必要
6.成年後見制度の利用
・認知症により判断能力が十分でない場合は、家庭裁判所に申立てて「成年後見人」を選任してもらう必要あり
→成年後見人は、リフォーム工事やその契約行為を代理で行う法的権限を持つ
7.リフォーム内容によっては補助金制度もあり
・高齢者・認知症の方のためのバリアフリー改修などを行う場合、自治体の補助金や介護保険制度による給付が使える可能性がある
(例:手すりの設置、段差解消、トイレの改修など)
✅ まとめ:リフォームの進め方(判断能力がない場合)
・家の名義を確認する
・可能ならば補助金なども申請
・リフォーム会社に相談する前に、地域包括支援センターや弁護士・司法書士に相談
・認知症の診断書などで判断能力を確認
・必要であれば、家庭裁判所に成年後見人の申立て
・後見人の選任後、契約・工事実施
・当社のお客様の多くが40代後半から60代前半の会社員が多く、その方たちが自分自身の老後生活設計についてご相談にお越しいただいています。
この方たちには親御さんがおり、70代から90歳代です。この親御さんたちはまだまだお元気な方もいますが、80代90代になるとそろそろボケてきたかも・・・
また既に介護状態の方もたくさんいらっしゃいます。
この親の世代が自分たちで天寿全うまで自立自己完結してくれないと、子の世代が少なからず時間も労力も経済的にも負担することになります。
自身のライフフランが成り立たないと言う事態すら生じてきます。
そんな状況の中で、親御さんの法定後見・任意後見・家族信託・遺言書作成などのコーディネートさせて頂くことも増えてまいりました。
うちの親怪しいな・・・と思ったら是非ご相談ください。
