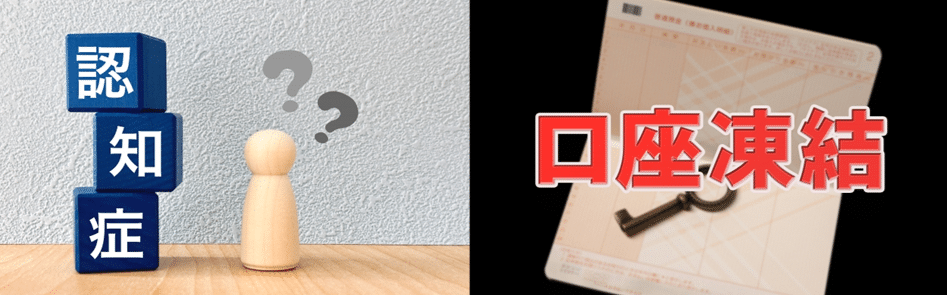 銀行では、認知症の方の取引をめぐり「本人の意思確認」と「資産保護」の両立が求められます。
銀行では、認知症の方の取引をめぐり「本人の意思確認」と「資産保護」の両立が求められます。
ここでは、銀行の基本的な対応方針と実際に起こり得る流れを整理します。
1. 本人確認の段階で対応が分かれる
銀行は法律上、本人確認(身分証明・意思確認)を厳格に行う義務があります。
そのため、窓口職員が応対時に「認知機能に問題がありそう」と感じた場合、次のような対応を取ります。
● 本人の意思確認が不十分と判断された場合
銀行は取引を保留または拒否することがあります。
(例)預金の引き出し、大きな振込、解約、定期預金の解約など
「家族の同席」「後見人の確認」「代理人カード・委任状」の提示を求められます。
状況によっては、警察やケアマネジャーなどへの連絡を検討する場合もあります。
● 本人が理解していると判断された場合
少額の引き出しや残高照会など、本人の意思でできる範囲の取引は応じてもらえることがあります。
ただし、職員が少しでも“判断能力に疑義あり”と感じた場合は、慎重な対応になります。
2. 家族が付き添っている場合
銀行は「家族=代理人」とは扱いません。
→ たとえ配偶者や子であっても、法的代理権がなければ口座操作はできません。
対応としては次のようになります。
- 事前登録制の「代理人カード」や「委任状」での取引は可能。
- 認知症が進行し、本人の意思確認ができない場合は「後見制度(家庭裁判所の手続き)」を案内されます。
3. 法的な手続きが必要になるケース
本人の判断能力が低下し、意思確認ができない場合、
銀行は「成年後見制度」などの法的枠組みが整うまで取引を停止するのが原則です。
成年後見制度の主な種類
法定後見制度:家庭裁判所が後見人を選任。預金管理・解約などの手続きが可能。
任意後見制度:本人が元気なうちに、将来に備えて契約を結んでおく仕組み。
後見人が選任されると、銀行口座は「後見人名義での取引」に切り替わります。
4. 実際の窓口での対応例(現場の声)
「ご高齢の方で受け答えがちぐはぐだったため、本人確認を慎重に行い、取引を一旦お預かりした」
「ご家族から“認知症で心配”との事前相談を受け、後見制度の案内をした」
「定期預金の解約を求められたが、ご本人が理解できていないと判断して対応を保留した」
銀行は「本人保護」および「不正防止」の観点から、疑いがある場合は必ず慎重に対応します。
5. 本人の状況と銀行の対応(整理)
本人の状況 ➡ 銀行の対応
本人が理解している ➡ 通常通り対応(ただし慎重)
判断が難しい ➡ 取引保留・家族や代理人の確認
判断できない ➡ 取引停止、後見制度の案内
家族のみ来店 ➡ 委任状・代理人カードがなければ不可
6. 家族ができる事前対応
代理人カードの発行 ➡ 本人が元気なうちに、信頼できる家族を代理人として登録しておく。
家族信託の利用 ➡ 将来の認知症リスクに備え、財産管理を信託契約で委ねる。
成年後見制度の準備 ➡ 認知症が進んだ場合に備え、任意後見契約を検討しておく。
まとめ
認知症の方が銀行窓口に行った場合、銀行は本人の意思を尊重しつつ、資産を守るために慎重な対応を取ります。
家族としては、「代理人登録」「家族信託」「後見制度」などを早めに準備しておくことが、親の財産を守る第一歩です。
元気なうちに話し合い、安心して暮らせる仕組みを整えておくことが、何よりの備えと言えるでしょう。
あおばファイナンシャルプランナーズでは終活のご相談も承っております。
少しでもご心配の方はお気軽に無料相談をご利用ください。
